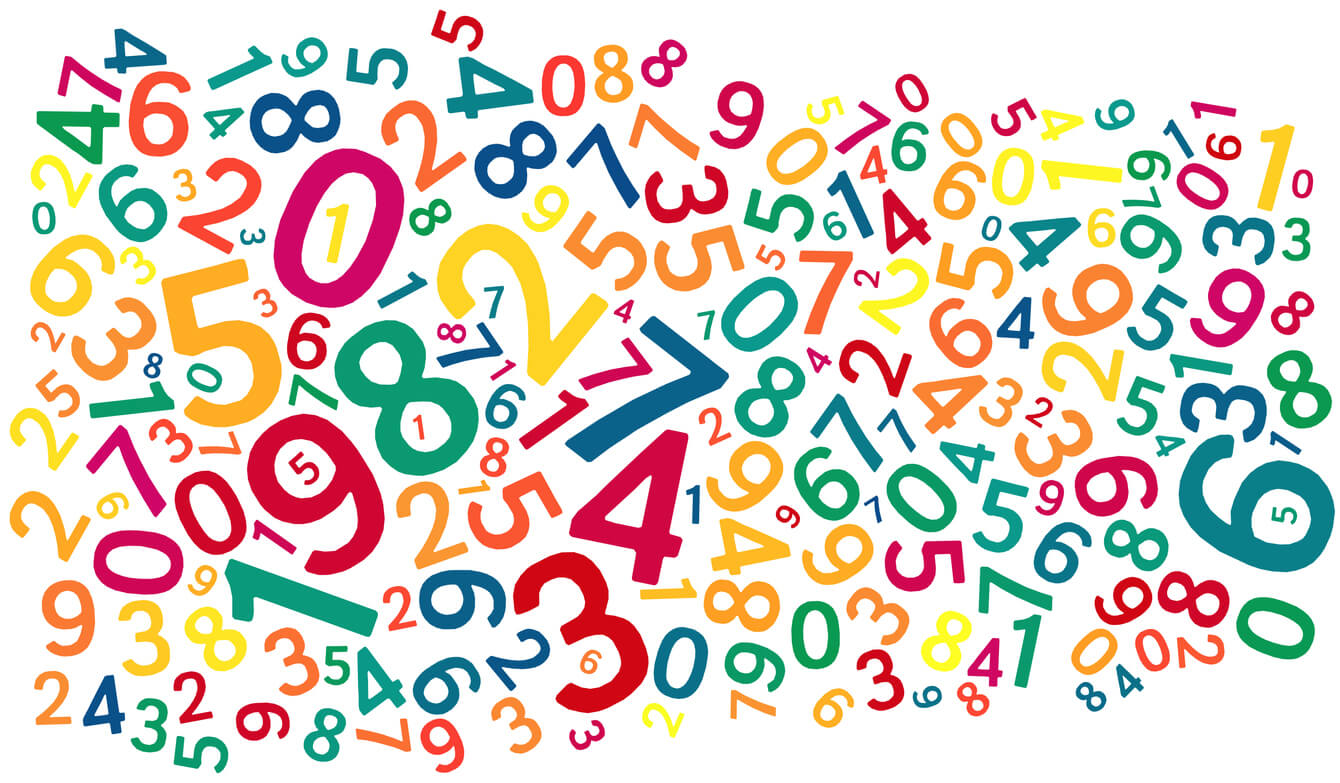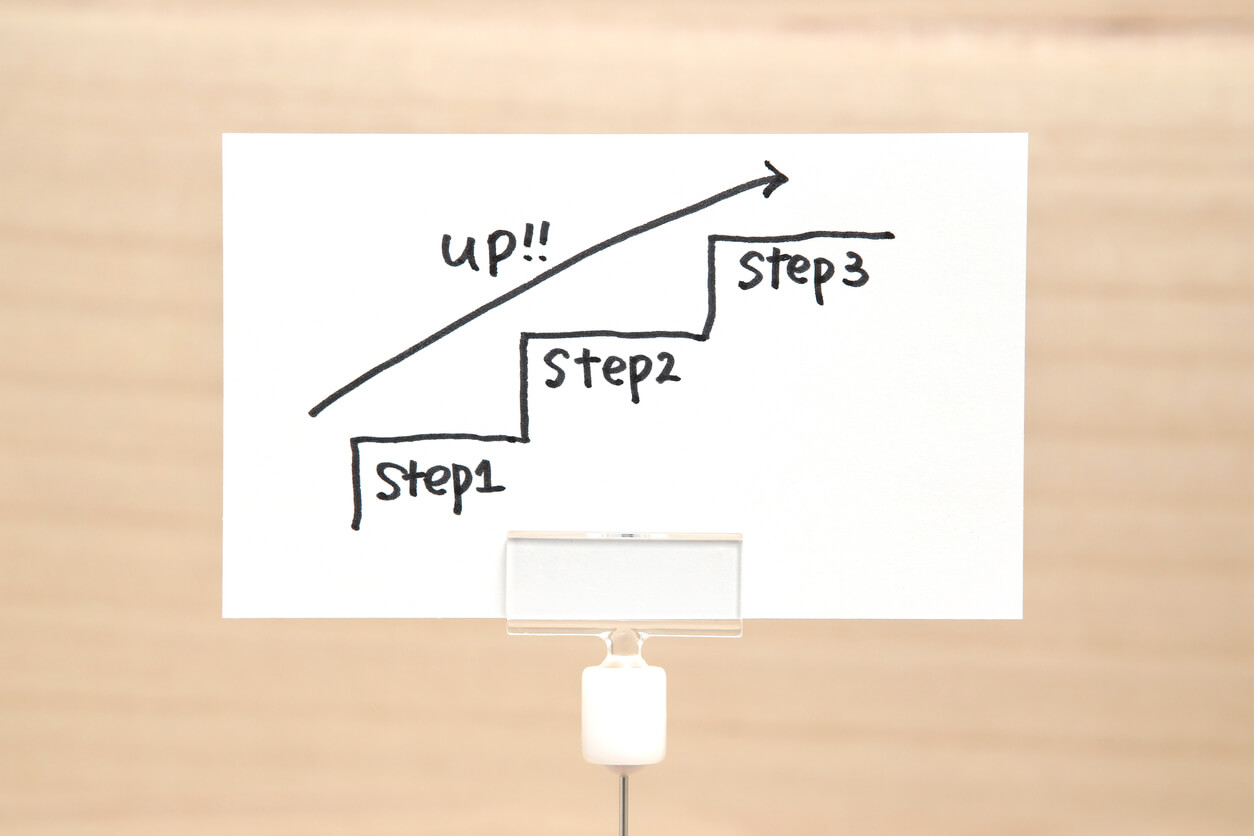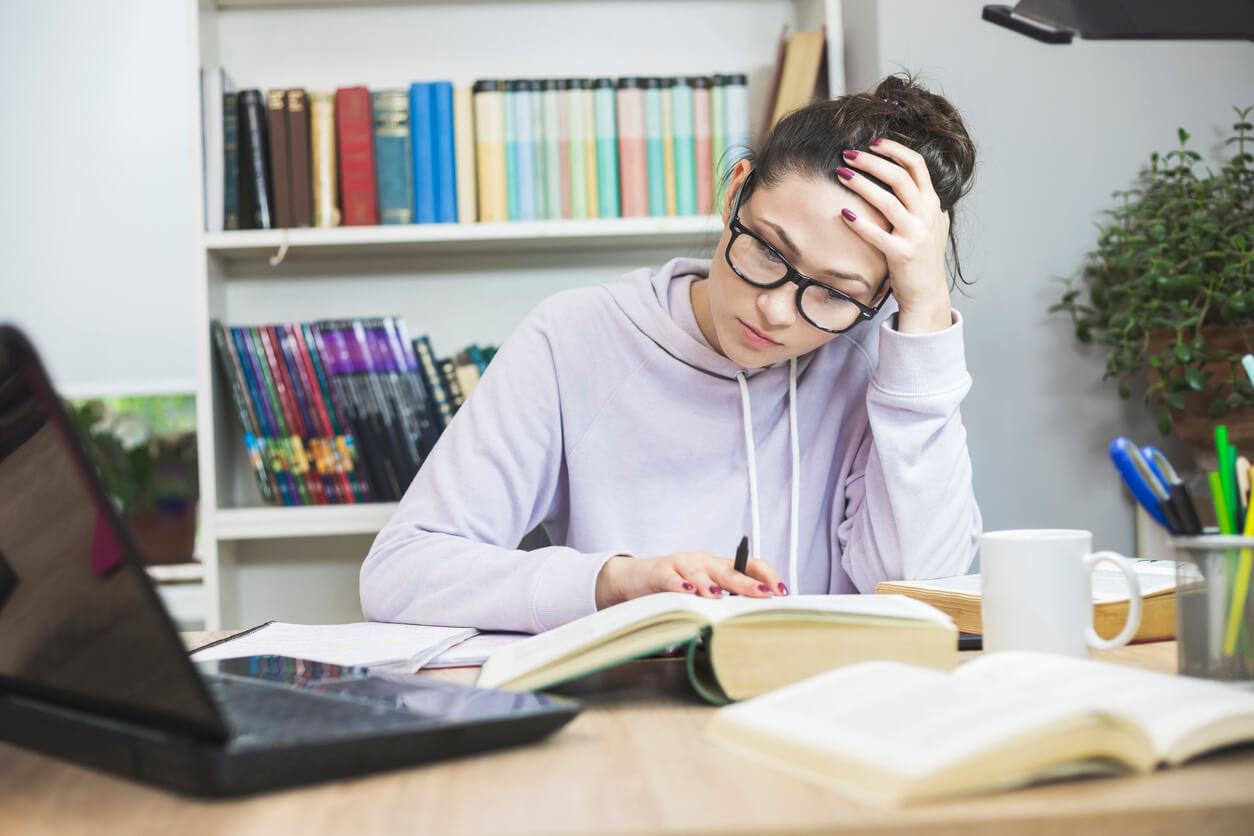日本語の文章では算用数字と漢数字の使い分けが重要なポイントで、うまく使い分けることができると文章は読みやすくなります。しかし実際に執筆してみると、どちらを使うべきかとまどうこともあるのではないでしょうか。そこでこの記事では、数字の書き分けについてのルールと実際の書き分け例を紹介します。
算用数字と漢数字の基本的な3つの表記ルールとは
算用数字と漢数字との使い分け方には、大きく3つのルールがあります。具体例を交えながら順番に見ていきましょう。
縦書きと横書きの違い
日本語の書き方には縦書きと横書きがあります。前者が昔ながらの伝統的な書法であるのに対し、後者は江戸時代後半から明治時代にかけてヨーロッパの影響を受けて使われるようになった書法です。
そのため数字の記載についても、縦書きでは昔から使われてきた漢数字で記述する一方、横書きでは同じくヨーロッパから入ってきた算用数字で記述するというのが大まかなルールになっています。また媒体ごとにも傾向があり、新聞や書籍などの伝統的なメディアでは縦書き、つまり漢数字が主流ですが、インターネット上の文章や履歴書では横書き、すなわち算用数字が主流です。
実際の例として、住所を例に考えてみましょう。履歴書のような横書きの文章では「6丁目8番」や「~マンション507号室」のように算用数字で住所を記載することが一般的ですが、年賀状や封筒を送る場合などのような縦に住所を記載する場合には、「六丁目八番」「~マンション五○七号室」と漢数字を使って書くことになります。なお、一般的にゼロの表記は「零」ではなく「○」とします。
固有名詞や熟語の場合
横書きでは原則として算用数字が使われるとしましたが、だからといって必ずしも算用数字だけを使うわけではありません。
その例外の代表的なものが、数字が含まれている固有名詞や熟語です。日本の地名や人名には数字が含まれていることも多くありますが、それらは常に漢数字で書かれます。「東京都八王子市」、「九州地方」などの地名を「東京都8王子市」、「9州地方」と書くことはありませんし、「三田佳子」を「3田佳子」と書くこともありませんよね。
また、熟語などのようなひとまとまりの言葉の一部分に数字が出てくる場合にも、同じことが言えます。例えば、「百戦錬磨」、「七転八倒」という熟語を書くときに「100戦錬磨」、「7転8倒」とすることはありません。さらに「一気に終わらせる」、「一斉に手を挙げる」というような副詞表現についても、「1気に終わらせる」、「1斉に手を挙げる」という記述はしませんので、注意しましょう。
特殊な表現や併用可能なケース
ここまでは漢数字と算用数字の片方が正解になる場面を取り扱ってきましたが、このほかに、どちらの方法で記述しても意味が通じる用語もあります。例えば、「二大政党制」と「2大政党制」、「日系二世」と「日系2世」などの場合には両方の記述が混在しており、どちらでも意味は同じですし、特に明確な線引きもされていません。
一方、漢字で書いても算用数字で書いても意味は通るものの、それぞれの場合で意味が異なるという事例もあります。このような場合には、大まかなルールとして、数や量を表すために数字を用いる場合には算用数字を使い、それ以外の目的であれば漢数字を使いましょう。従って、迷ったときには「数字の部分を他のものに置き換えても意味が通りそうなら算用数字を利用する」と考えて判断すれば概ね問題はありません。
具体例を見ていきましょう。固有名詞で紹介した「九州」の場合、もしも「9州」と記述した場合には、単に「9つの州」という意味のフレーズになるため、「◯◯党はカリフォルニア州などの9州で過半数を獲得した」という文章ならば算用数字がふさわしいということになります。またこのほかにも、「いちにんまえ」という言葉について、「一人分の量」という意味を表したい場合には「1人前」とし、「人並みの技量がある」という意味を表したい場合には「一人前」とします。
そのため、「彼は一人前の職人だ」とはできますが、「彼は1人前の職人だ」とはできませんし、「お寿司を1人前頼んだ」は自然ですが、「お寿司を一人前頼んだ」は不自然になります。ただしこのルールにも例外があり、数や量を表す場合でも「一つ」「二つ」のような古くからあるものの数え方であれば漢数字で表記する方が自然だとされています。
実際の使用例を確認してみよう
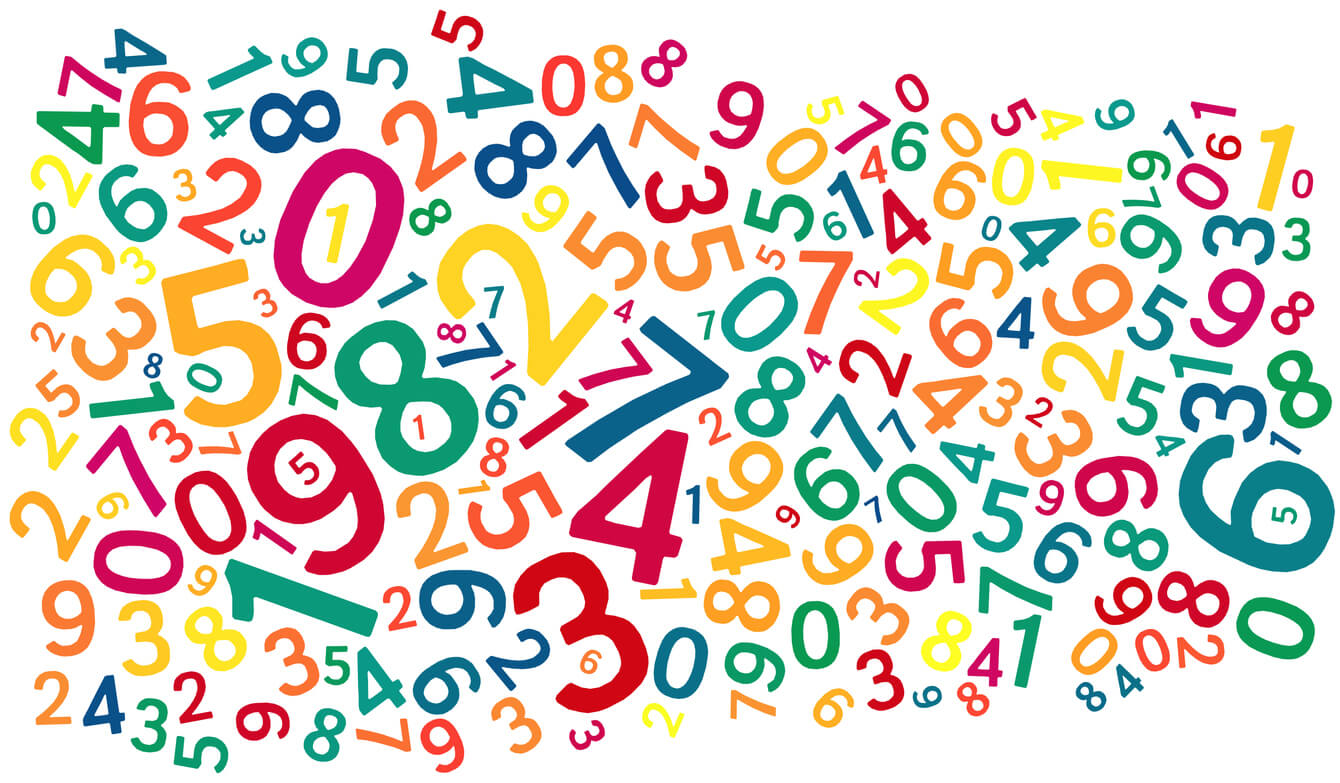
ここまでは、数字の書き方に関する二つの手法について、大まかなルールを紹介しました。ここからは、具体的な場面での使用例をさらにいくつか確認しましょう。
年数の表記
「1968年生まれ」のように西暦で表記するときだけでなく、「平成29年卒業」のような和暦で表記をするときも、履歴書など横方向に書く文章であれば年月日には算用数字を利用します。年月日は数や量を表すものだからです。同じ理由で、電化製品の「5年保証」、賃貸の「4年契約」のように経過年数を表す場合や、「小学6年」「大学4年」のような年次を表す場合にも、算用数字が利用されます。一方、年数に関連した内容であっても、「十年一昔」や「一年中」のような熟語フレーズの場合には漢数字が利用されます。これもすでに紹介した原則通りです。
資格試験の区分
横書きの文章でも、特に履歴書などでは資格や検定試験の級を記載する場合があります。この場合、「級」であれば「英検1級」や「漢検2級」のように算用数字を利用することが一般的です。ただ、資格であっても剣道や柔道、囲碁、将棋などで「段」「級」を使う場合には、「アマ三段」「剣道五段」などのように漢数字が使います。
Excel資料やデータの数字
Excel資料やデータなどの数値を参照、言及するときには、すでに紹介した原則通り、数や量を表すための数字なので算用数字で表記します。ただし、桁数が大きくなると読みにくいため、量を表す数字の場合には3ケタ毎にコンマを入れて区切るやり方もありますが、商品の型番など量を表していない数字に対してコンマ区切りを使うことができません。
また、文章においてケタの大きな数字を記載する場合には、「万」や「億」などの大きなケタの単位を漢数字で表して、「5万円」や「1億2,500万人」のような漢数字と算用数字の混じり表記とすることがありますが、これも厳密なルールではないので、執筆者が読みやすさを考慮して柔軟に対応すべきものです。
算用数字や漢数字を使用する際の注意点
ここまで見てきたように、算用数字と漢数字の使い分けについては、比較的わかりやすいルールがある場合もあれば、必ずしも正解が一つにはならない場合もあります。そして、自分で文章を書くうえでは、適切な使い分けをしつつも統一感を持たせるということが大事になってきます。したがって、どちらか片方が明らかな正解であるときは正しい方を使うのは当たり前ですが、必ずしもどちらかが正解とは言い切れないときは、文章の中での表記を統一することに気を配ってください。両方の記述を混在させてしまうと、読者にとって違和感のある読みにくい文章になってしまうからです。
例えば、ある文章の中で最初に「二大政党制」と書いたら最後まで「二大政党制」で通し、途中で「2大政党制」という書き方をすることは避けなければいけません。同様に、最初に「50,000人」と書いた場合には、途中で一部だけ「5万人」や「50000人」とすることは避けて、最後まで「50,000人」で統一してください。
このように算用数字と漢数字の使い分けや表記ルールを紹介してきました。今後、文章を書いていて数字と出会ったときには、この記事に記載されているルールを意識しながら、読みやすさに配慮したわかりやすい文章を書くように工夫してみてください。
Webライティングを行っている方のなかには、基礎が曖昧なまま記事を書いてしまっている方もいるでしょう。しかし、Webライティングには基本項目がいくつかあります。意識して書くと分かりやすくて読みやすい文章になるでしょう。さらに、よりステップアップするためのポイントを押さえて、ライティングスキルをアップさせましょう。
Webの文章の特徴とは
Webページには、検索結果で上位に表示されないと閲覧数が増えないという特徴があります。 インターネット上には数え切れないほどのWebサイトがあります。しかし、キーワードを検索したときにトップページに表示されるサイトはごくわずかです。
検索結果で上位のサイトでなければ人の目にとまることが少なく、閲覧数も減ってしまうでしょう。そのため、Webの文章はトップページに表示されるようなものであることが求められます。
また、Webサイトは簡単にページを移動することができます。さまざまなサイトを見比べたいという理由や、いつでも読むことができる手軽さから、すぐにサイトを離脱して移動する人が多いです。そのため、Webの文章はなるべく離脱・移動されないようにさまざまな工夫を行う必要があります。
Webライティングの主な目的は「SEO」
Webライティングの記事の多くが目的としているのが、「SEO」とよばれるものです。SEOとは、検索エンジンで何かを検索したときに表示される結果リストの中で、上位に表示されるように工夫を凝らすことを指します。
ただし、どんなWebサイトが上位に表示されるのかということを明確に示している検索エンジンはほとんどなく、評価方法も頻繁に変わっているとされているため確実な対策方法は分かりません。とはいえ、どのような工夫を凝らすことが有効であるかということを推測することは可能です。
SEOで大切なことは、読者が検索したキーワードに沿った内容を書いて、ニーズを満たすことです。そのためには、読者がなぜ検索したのかという意図を予測して、求めている情報を求めている量だけ提供することが重要です。
読者が欲しい情報を提供するために、検索結果上位に並んでいるサイトの内容やタイトルを調査して参考にしましょう。ただし、内容や構成をそのままコピーすることは厳禁です。あくまでも参考にとどめて、オリジナルの文章を書いてください。
さらに、情報量についても上位に並んでいるサイトをいくつか調査しましょう。どのような情報をどのくらいの量で書いているのか調べると参考になります。少なすぎると薄い内容になり、多すぎると最後まで読まれない可能性があるため分量には注意してください。
Webからの訪問者は、興味がないとすぐ離脱する
読者が何らかのキーワードを検索するのは、情報が欲しいときです。正確な情報を得るためにいくつかのサイトをまわる人も多いでしょう。そのため、Webサイトを訪問しても内容が面白くない、ためにならない場合はすぐに離脱してしまいます。
特に、スマートフォンで閲覧すると画面が小さくて全てのページを読むのに時間がかかります。そのため、少しでも興味を失うと読者は途中で離れてしまうでしょう。
また、欲しい情報が書いてなかったり、書かれていることでさらに疑問が生まれたりした場合も離脱して違うサイトに移動してしまいます。
そこで、求められている情報をしっかりと盛り込んで読者のニーズを満たす必要があります。 さらに、どこにどのような情報が書いてあるのかをはっきりさせることも重要なので、見やすくなるように工夫しましょう。目次や見出しなどを効果的に使用することをおすすめします。
面白いと感じた記事は拡散される
面白いと思われた記事やしっかりとした情報が載っていると感じられた記事は、SNSを通して拡散されることがあります。 特に、フォロワーが多くて拡散力が大きい人、いわゆるインフルエンサーが拡散すると瞬く間に日本中、世界中に情報が広がっていきます。その結果多くの人々に見てもらうことができるため、拡散されやすい記事を目指すことが大切なのです。
Webライティングの5つの基本ルール
Webの文章は、簡潔に書いて誰が読んでも理解しやすいように書くことが大切です。そのためにはいくつかの基本項目があるので、解説しましょう。
1.結論は先に書く
基本的に、結論は説明や理由よりも先に書きましょう。Webの記事は、パソコンでもスマートフォンでも上から下に読まれます。そのため、結論が一番下にしか書いていない場合、そこまでたどり着く前に読者が離脱する可能性が高いです。
また、読者は情報を得るために検索し、Webサイトを訪れています。結論だけが知りたい場合もあるため、結論を先に提示すると好まれる記事になるでしょう。結論を知った上で理由や説明も読みたい場合や興味がある場合は、読者が上から下へと読み進めていってくれるでしょう。
2.接続詞を意識して、前後の段落の関係性を明確にする
分かりやすい文章にする上で、接続詞を意識することは非常に重要です。なぜなら接続詞を入れることで、前の文と後ろの文の関係性がはっきりするためです。
例えば、前の文と反対の意味の文章を書きたいときは「しかし」など逆説の接続詞を入れます。前の文で理由、後ろの文で結果を書きたいときは「そのため」など順接の接続詞を使います。そうすることで文章の流れを掴みやすく、読みやすくなるでしょう。
特に、情報をたくさん入れたいときには接続詞を効果的に使用する必要があります。内容と関係がなさそうな文章が続くと、読者は飽きて離脱してしまいます。そこで、文章を入れるときには前の文や前の段落との関係性を明確に示しましょう。
なお、接続詞の中には「しかしながら」などかたい印象を与えるものもあります。そのため、接続詞は文体や内容に合わせてさまざまな種類を使い分けるとよいでしょう。
3.誤字・脱字をなくす
Webの文章はパソコンなどで書くことが多いため、タイピングミスなどで誤字・脱字が発生しやすいです。誤字や脱字があると読みにくい文章になるため十分に注意しましょう。
特に気をつけたいのは、同音異義語の変換ミスです。例えば「橋」「端」「箸」など、同じ音でも漢字によって大きく意味が変わるものは変換ミスが起こりやすいため注意が必要です。
なお、変換ミスではなくそもそも誤った意味で覚えて使ってしまう場合もあります。「採る」や「摂る」など、使い分けがややこしくて迷う場合はその都度調べましょう。
誤字脱字をチェックするためには、校正機能などを活用すると便利です。Wordにも校正機能があり簡単に使うことができるため、ぜひ利用してみてください。
さらに、提出前には目視でもしっかりと確認しましょう。流し読みではなく、一字一字確認することが大切です。
また時間があるときは、記事を書いた翌日に最終チェックを行うことをおすすめします。そうすることで自分の書いた文章を客観的に読むことができて、誤字脱字に気がつくことができるだけでなく、分かりにくい表現にも気がつきやすいでしょう。このように誤字脱字や分かりにくい表現を訂正することで、文章の質を向上させることができるに違いありません。
4.最初に構成を練っておく
文章を書くときには、まず始めに構成を考えておきましょう。そうすることで、話が飛躍することを防ぐことができます。また、記事のターゲットや言いたいことを整理しておくことで、簡潔で分かりやすい文章を書くことができるでしょう。
また、内容を書く前に見出しを作ってしまうという方法によって、記事全体の流れが掴みやすくなります。
さらに、段落ごとに言いたいことを決めておくと書きやすくなるでしょう。概要ごとに例を挙げていくとイメージしやすくて具体的な文章になります。
5.一文が長すぎないようにする
Webの記事は一文が長くなりすぎないように注意しましょう。読者が、スマートフォンなど画面の小さい端末で読むことがあるためです。一文がだらだらと長いとスクロールの回数が多くなるため、内容が理解しにくくなります。
読点が多く続く場合は、リズムを付けるように一度句点を打って文章を終わらせましょう。一文は、できれば40文字から60文字程度にすることをおすすめします。長すぎず短すぎない文章を心がけると良いでしょう。
Webライティングの基本からステップアップするためのポイント
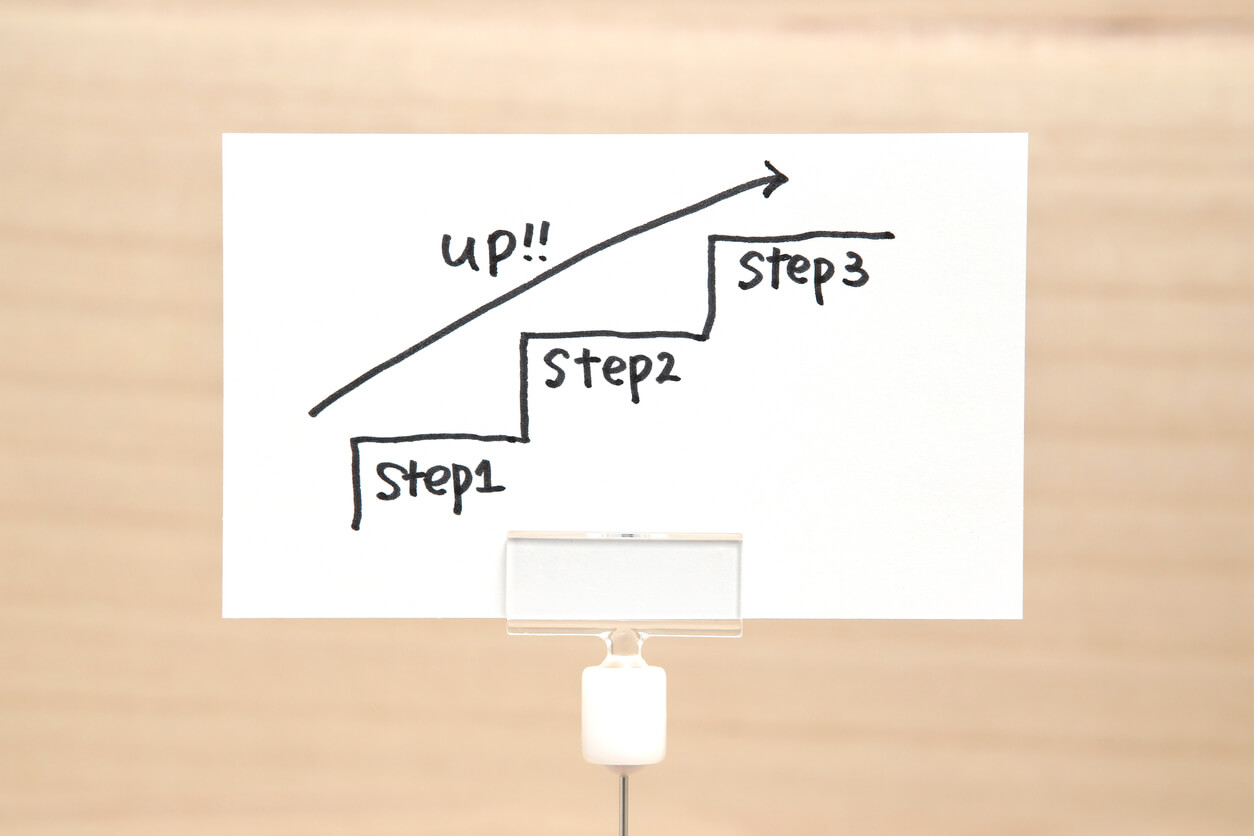
Webライティングの基本が分かって身についてきたら、さらにステップアップしたいという方は多いでしょう。まわりのライターと差をつけるためのポイントがいくつかあります。
読者に「この記事を読むとどんなメリットがあるのか」を与える
記事を書く上で大切なことは、読者に、「この記事を読んで良かった」と思ってもらうことですよね。そう思ってもらうためには、読みながら内容をイメージしやすい記事を書くことが重要です。そのために、具体例や数値、データなどを積極的に使いましょう。
具体例がないと、抽象的で分かりにくい文章になります。結局何が言いたいのか、実際にどのような効果が得られるのかなどを明確に示しましょう。1つの見出しに1つの具体例を示すと分かりやすくなります。
また数値やデータは、具体的な内容の文章を書くことに役立ちます。例えば、「たくさんの人が利用しました」と書くよりも「100万人の人が利用しました」と書くほうがイメージしやすい文章になるでしょう。また、数値を書くときには「だいたい」や「約」をあまり多用せずに、正確に書くことを心がけましょう。
なお、数値やデータは信頼できる情報をもとに書くことが必要です。省庁が発表している数値や専門家が提示しているデータ、企業の公式サイトのデータなどから情報収集しましょう。
一方、個人ブログや誰でも編集できるようなサイトは信頼性が薄いため注意が必要です。どのサイトの情報を使用するか迷った場合は、最も信頼性が高い公的機関の数値やデータを使うと安心でしょう。
読者が「知りたいこと」をしっかり調査する
読者が検索するであろうキーワードに寄り添った内容の記事は、検索結果上位に表示される可能性があります。SEO対策としても、読者が知りたいことを調査することは重要です。
そのために、どのキーワードで上位に載りたいのかということをあらかじめ決めておきましょう。読者が知りたいことを予想すると決めやすいです。その上で実際に検索してみて検索結果上位のサイトを調査すると、盛り込むべき内容が分かります。構成の参考にもなるでしょう。
さらに、上位のサイトに載っていない情報を含めることでオリジナリティを出すこともできます。必要な情報は載せながらも、独自の記事を書いて差が出るように工夫しましょう。
語尾にバリエーションをつけて、読みやすい文章になるよう工夫する
同じ語尾が何度も続くと、そっけない印象の文章になります。同じ語尾の連続は、なるべく2回程度に抑えましょう。特に、「です」「ます」が続くと単調で読みづらいです。そのため、「~でしょう」などの語尾も積極的に使用して工夫しましょう。
やわらかいトーンの文章を書く場合は、「~ですよね」といった共感の語尾を使うこともおすすめです。しっかりとメリハリを付けて読みやすい文章を目指しましょう。
「改行」をしっかり行う
文章に改行がないと、文字がずらずらと並んでいるように見えて読み手にストレスを与えます。基本的には5、6行書いたら1度改行を入れるようにしましょう。
改行を入れるときの注意点としては、内容が変わったときに入れることが挙げられます。同一の話題の途中で改行を入れると途切れた印象になります。
また、読みやすくしようとして頻繁に改行しすぎてしまうとかえって読みづらくなるでしょう。改行を入れるタイミングには注意してください。
さらに、スマートフォンで閲覧したときのことも意識しましょう。パソコンでは見やすくても、画面が小さいスマホで見ると文字が詰まっている印象を与えることがあります。プレビューを見ることができる場合は、パソコンとスマホ両方を使って確認してみましょう。
自分の文章を最後に「音読」する
文章が完成したら、最後に音読してみましょう。そうすることで、自分が書いた文章のリズムを掴むことができます。リズムが良い文章はスラスラと読みやすい文章でもあるため、読者のためにもなります。
さらに、誤字脱字を見つけやすいというメリットもあります。音読することで、黙読するよりも注意深く文章を読むことができるためです。
また、声に出して読むことで連続した語尾にも気がつきやすいです。自分で読んで違和感がある文章は、人が読んでも違和感を覚えます。そのため、違和感を感じた文章はしっかりと修正して、読みやすい文章になるように改善しましょう。
以上の内容をしっかりと押さえると、Webライティングのスキルがアップするでしょう。いきなり全ての内容をマスターすることは難しいので、まずはできそうなポイントから始めてみてください。
ライティングの際に、助詞の「てにをは」を自信を持って完璧に使いこなせるという方は非常に少ないのではないでしょうか。たった1文字の違いで文章のニュアンスを変えてしまう「てにをは」。今回は、そんな難しい助詞の使い方や上手に助詞を使いこなすポイントについて紹介します。
「てにをは」の由来って?
日本語の助詞「てにをは」は、日本語を学ぶ外国人にとって特に難しい文法の一つだと言われ続けています。たった1文字違うだけでその文章の意味や印象を変えてしまう「てにをは」は、日本人にとってでさえ難しいのではないでしょうか。
たとえば、以下のような文章があったとします。
「彼は彼女を褒めた。」
この文章からは、読んで字のごとく、彼が彼女のことを褒めたということがわかります。しかし、この文章からたった2文字だけ助詞を変えただけで全く意味の異なる文章になることがわかります。
「彼を彼女が褒めた。」
助詞をほんの少し変えただけですが、途端に文章の主語は「彼」から「彼女」に変わり、全く違う内容の文章になってしまいました。日本語のネイティブであれば、特別な勉強をしなくとも、この程度の助詞の用法はわかりますが、長い文章を書く際や少し説明が難しい内容を説明しようと試みるときに、「てにをは」を間違えて使ってしまう方も少なくありません。日本語を学ぶ外国人であれば、それぞれ「てにをは」を使うときのルールを細かく学びますが、日本人は生まれたときから自然に「てにをは」を覚えるので、なかなかそのルールについて説明できる人はいないのではないでしょうか。
今回は、そんな使い分けが難しい助詞の「てにをは」について、解説していきます。
日本語の助詞には、「てにをは」以外にも、「で」「も」「が」「へ」など多数の助詞があります。それでは、なぜ助詞全体のことをまとめて、「てにをは」と言うことが多いのでしょうか。日本語の独特の文法である「てにをは」の歴史は古く、漢文から来ています。ここからは、「てにをは」の由来について詳しく見ていきましょう。
漢文と「てにをは」の関係
助詞をまとめて「てにをは」と呼ぶのは、漢文を読む際の「ヲコト点」に由来しています。ヲコト点とは、漢文を訓読するときに、漢字の読み方を表すために記入されていた符号です。ヲコト点は「乎己止点」や「遠古登点」とも表記することができます。ヲコト点は、漢字の四隅や中央、外側などに位置づけられています。そして、その訓点を四隅の左下から時計回りに読むと「テニヲハ」となることから、日本語の助詞のことを指して「てにをは」と呼ぶようになりました。
このヲコト点は平安時代初期から室町時代まで使われており、その後は「かな点」を使用する漢文の読み方が主流になったものの、現在の日本語の形成に大きく貢献したといえるでしょう。
そもそも「てにをは」の意味とは
先ほどご紹介した通り、「てにをは」の由来は漢文にありますが、一般的に「てにをは」といえば、日本語の助詞全般のことを指すことがほとんどです。日常会話の中では、「この文章は、てにをはがなっていない」「あの人の話す言葉は、てにをはがわかりにくい」などという使い方で使うことが多いのではないでしょうか。
実際に、「てにをは」は日本語の助詞全体のことを指すので、「て」「に」「を」「は」以外にも、格助詞の「の」や「と」、接続助詞の「ので」や「から」、副助詞の「も」や「ばかり」などの助詞について説明するときも「てにをは」という言葉を用います。
「てにをは」の助詞としての用法4つと注意点
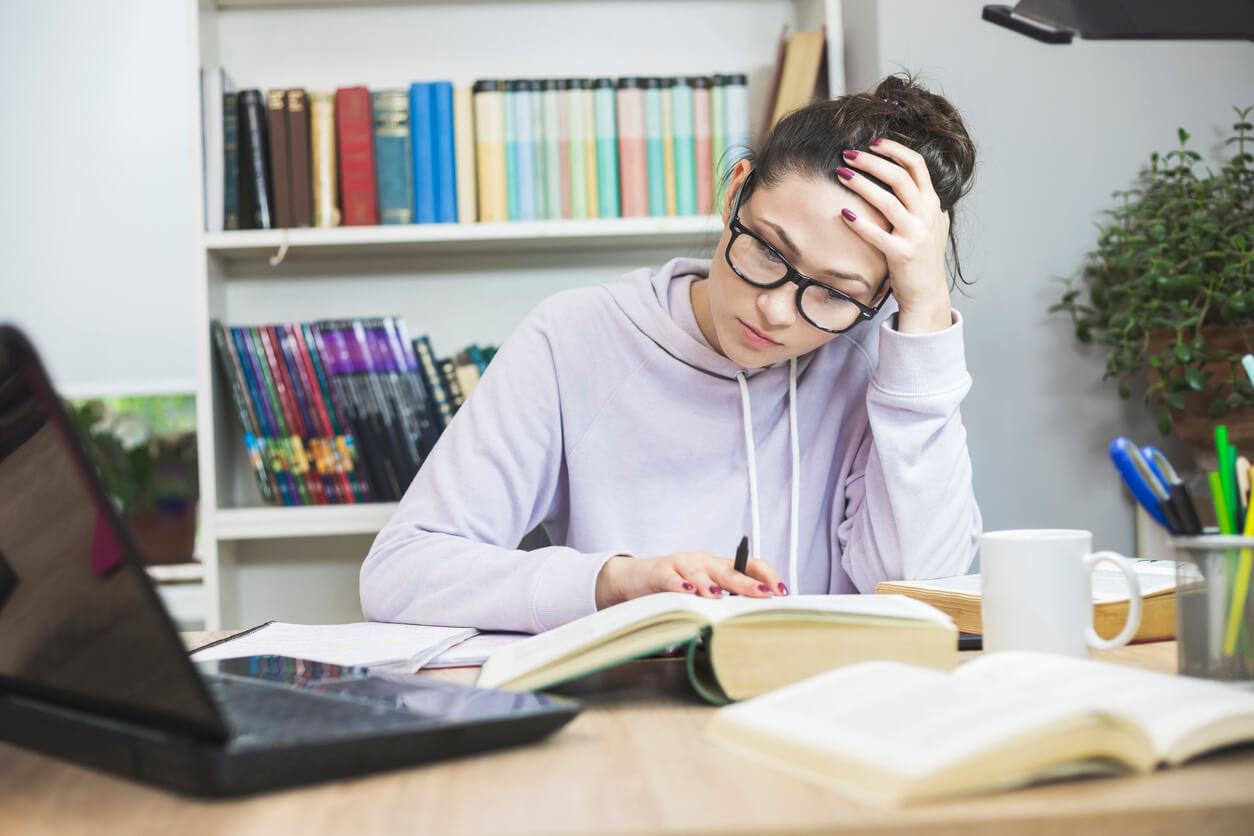
ここからは、助詞の「てにをは」を文中で使用する際の用法を4つと、その助詞を使用する際の注意点を紹介します。Webライティングのみならず、どんな文章を書くときでも「てにをは」を正しく使うことが大切です。さらに、普段の会話でも「てにをは」がたった1文字違うだけで、相手に与える印象が変わってしまうので、やはり正しい助詞を使用することは日本人にとって非常に重要なことでしょう。
それでは、「てにをは」の用法と使用する際の注意点を、使い方の難しい助詞を2つずつ比較しながら見ていきましょう。
用法1.「~で」と「~を」
最初に紹介する助詞「てにをは」の用法は、「~で」と「~を」との違いです。まずはこちらの例文をご覧ください。
「お飲物は何がよろしいですか?」
「コーヒーでお願いします。」
一見、自然に見えるこの文章ですが、ここで「で」という助詞を使うことによって、相手に少し不快な思いをさせてしまう可能性があります。
もちろん、飲み物の希望を聞かれるような場面で、「で」という助詞を使うことは間違いではありません。しかし、このときに「で」という助詞を使ってしまうことによって、少し投げやりな印象を与えてしまいます。
では、「お飲物は何がよろしいですか?」などと、選択肢のある問いかけをされたときはどのように答えるのが良いのでしょうか。このような場合は、以下の助詞を使って答えてみるのが良さそうです。
「コーヒーをお願いします。」
こう答えることによって、私の飲みたいものはコーヒーです、と相手に誤解なく伝えることができます。 ライティングをする際も、何か自分の主張があり、読者に不明瞭な印象や投げやりな印象を与えないためにも、「~で」から「~を」に言い換えることができる文章であれば、可能な限り「~を」を使用するようにしましょう。
用法2.「~が」と「~は」
次に紹介する助詞の用法と使用時の注意点は、「~が」と「~は」についてです。この違いとてもややこしいため、感覚で使い分けている方がほとんどなのではないでしょうか。では、こちらの例文を見分けてみましょう。
「最後の文章がよかったよ。」
「最後の文章はよかったよ。」
もちろん、どちらの文章も日本語としては正しいので、どちらを使っても意味は通ります。しかし、気を付けなければいけないのは、どのような文脈で使うかという点です。
お気づきの方も多いかと思いますが、1つ目の「最後の文章がよかったよ。」という文に比べて、2つ目の「最後の文章はよかったよ。」という文章は、まるで最後の文章以外はダメだったかのような印象を相手に与えてしまいます。
特に話し言葉で、「~は」を強調して話すと、「最後の文章はよくても、他の文章はよくない」と暗に示す話し方になるでしょう。書き言葉の場合、文章の受け取り方は読み手に委ねられている部分が大きいですが、やはり多くの人は「最後の文章だけがよかったんだ」と受け取ってしまいます。
称賛の言葉を相手に伝えるときは、「~は」よりも「~が」を使用すべきです。大変難しい「~が」と「~は」の使い分けですが、この用法をしっかりと理解した上で会話に取り入れれば、自然と人から好かれるような話し方を手に入れることができるでしょう。
用法3.「~に」と「~を」
続いては、「~に」と「~を」の使い分けを紹介します。「に」と「を」をどちらも使うことができる日本語の文章は非常に多く、どちらでも意味は通じるため、あまり深く考えたことがないという方がほとんどでしょう。それでは、例文を基に解説していきます。
「私はいつもお金のことで両親に頼ってばかりいる」
「私はいつもお金のことで両親を頼ってばかりいる」
一見、上の文章はどちらも同じ意味、ニュアンスで捉えられるような気がしますが、実際は少しニュアンスが異なります。
「両親に頼る。」の場合、両親が「力を貸してくれるものとして依存できる対象」というニュアンスが強くなります。そして、「両親を頼る」の場合は、「助けになるものを求めてそこへ行く」というニュアンスになります。したがって、「に」を使った場合は、距離的にもしくは心理的に近い場所に両親がおり、いつも依存しているようなイメージになり、「を」を使った場合は、両親のことを頼ってお金を貰いに「行く」というイメージになるでしょう。
「~に」と「~を」の違いはこのようなニュアンスの違いではありますが、Web上に残るものとして文章を書く際にはしっかりと押さえておきたい違いですね。
用法4.「~から」と「~より」
最後に紹介する助詞「てにをは」の用法は、「~から」と「~より」の違いについてです。「~から」と「~より」との違いについては、ニュアンスや意味合いというよりも、使用する状況や文脈、使用する相手に応じて使い分けるのが良いでしょう。それでは、こちらの例文をご覧ください。
「本日は遠くからお越しいただきありがとうございます。」
「本日は遠くよりお越しいただきありがとうございます。」
こちらの2つの例文は、どちらも正しい文章です。しかし、上の文は比較的カジュアルな印象を読み手に与え、下の文はフォーマルな印象を読み手に与えます。したがって、目上の方に送る文章であれば、下の文章を使ったほうがマナーとしては良いでしょう。
一方、ライティングをする際に、カジュアルなトーンの文章を書く場合などは「~より」を使うと少し不自然になってしまいます。たとえば、「たくさんの食材が全国各地より集まって、美味しい料理ができているんですね!」という文章は、なんだか不自然な印象があります。このようなカジュアルなトーンの文章は、「~から」を使うのがベストでしょう。
常に「てにをは」を正確に使用するためのポイント3つ
助詞の「てにをは」は、たった1文字の違いでも、文章の印象ががらりと変わるということがおわかりいただけたと思います。ここからは、ライティングの際に、常に「てにをは」を正確に使用するためのポイントを3つ紹介します。日本人にとっても、常に正しい日本語を使うことは非常に難しいことですが、3つのポイントを押さえて、Webライティングに活かしてみてください。
読みやすい文章を書くライターをお手本にする
まず最初に紹介する「てにをは」を正しく使いこなすためのポイントは、読みやすい文章を書くライターの文章をお手本にするという方法です。この方法は、助詞の使い方をマスターするのに非常に有効な手段といわれています。なぜなら、文章が読みやすいということは、文章の構成や言葉の使い方が上手なだけでなく、しっかりと「てにをは」を使いこなせている証拠だからです。
普段文章を読んでいても、なかなか助詞の一つ一つに気を配る機会は少ないのではないでしょうか。そんな方は、ブログやSEO記事など、どんな文章でも良いので、読みやすくてお手本となるようなライターの文章をたくさん読んでみましょう。
読書量を増やしてみる
「てにをは」の使い方に自信がないという方の多くには、読書量が少ないという特徴があります。読書をして良質な文章を多く読んでいる方と、ほとんど読書をしたことがないという人とを比べると、やはり文章力に差が出てきてしまいます。
普段読書の習慣がない方にとっては、古典文学などは少しハードルが高いかもしれませんが、推理小説などのジャンルであればチャレンジしやすいのではないでしょうか。「てにをは」の使い方をマスターするには、たくさんの文章を地道にインプットしていくのが一番の近道です。読書する習慣が今まであまりなかったという方は、自分の好きなジャンルの本をたくさん読んでみましょう。
自分が書いた文章を人に見てもらう
最後に紹介する「てにをは」を正確に使えるようになるためのポイントは、自分が書いた文章を他人に見てもらうことです。なぜなら、自分の書いた文章だと、なかなか客観的な目線で添削することができず、普段誤用している助詞の使い方にも気づくことができない可能性があるからです。しかし、文章を他人にチェックしてもらうと、第三者の目線で客観的に見てもらうことができるので、自分の「てにをは」の使い方を正すチャンスになります。
自分が書いた文章を人に見てもらうという方法と併せて取り組んでおきたい方法は、他人の書いた文章をチェックするという方法です。自分以外の誰かが書いた文章をチェックすることによって、普段は特別注意を払わない「てにをは」の使い方に注意を払うことができるので、文章力の向上のためにもぜひ取り組んでみることをおすすめします。もし、知り合いの中にWebライターを目指している人がいれば、一緒に添削し合ってみるのも良いでしょう。
今回は、助詞「てにをは」の正しく使う方法について、いくつかの例を挙げて説明しました。慣れないうちは、助詞の使い方は非常に難しく感じられるかもしれませんが、一度慣れてしまえば自然と正しい「てにをは」を使うことができるようになります。
正しい「てにをは」の使い方にいまいち自信が持てないという方は、ぜひこちらの記事で紹介したポイントを押さえて、練習を重ねてみてください。
Webライティングにおいては、内容はもちろんですが「人に読んでもらえる文章を書くこと」が非常に重要です。なぜなら、どんなに良い内容が書かれていても読んでもらえないと意味がないからです。 そのため、多くの人に読んでもらう文章を書く技術がライターに求められます。そこで今回は、読みやすい文章を書くコツを解説します。
そもそも「読みやすい文章」とはどんなもの?
誰かに「読みやすい文章とは、具体的にどのような文章を指すのか?」と質問された場合、明確にコレとコレ、と答えられる方は意外と少ないですよね。なぜなら、私たちは普段それほど意識せずに文章を読んでいるからです。しかし読みにくい文章は読み飛ばしたり、結果的に最後まで読まなかったりしているはずなので、私たちは半ば無意識に読みやすさを判別しているのでしょう。
読みやすい文章を構成する要素はいろいろありますが、最終的には「視覚的にバランスが良い」文章が、読みやすいと評価されます。具体的には、段落ごとの分量が適切である、漢字とひらがなのバランスが良い、適度な改行があるなどの要素を含む文章を指します。
では、その「読みやすさの文章」についてもう少し詳しく見ていきましょう。
文字だけでなく「レイアウト」も意識する
意外かもしれませんが、文章はビジュアルも重要な要素です。たとえば改行がなく、ひたすら続く文章は非常に読みづらいものです。特にPCやスマホの画面上で読む文章は、改行がないと読み続けるのが苦痛に感じます。このため適宜改行を入れてあげると、読者が集中力を切らさないで最後まで読みやすくなります。
またWebの文章の場合は、段落の字下げをしないことが一般的で、代わりに段落と段落との間に1行分の空白が入るデザインにしているものが多く見られます。そのため改行するだけで視覚的にも見やすいレイアウトになります。
やってしまいがちなのは、印刷物用に制作した文章をそのままWeb用に転用してしまうパターンです。
印刷物用に作られた文章は紙面スペースの都合もあり、Web用の文章と比較すると改行が少ない場合がほとんどです。そのため単純に転用すると読みづらい文章になってしまうので、読みやすさを意識して改行や見出しを追加するといったひと手間をかけてあげるとよいでしょう。
ここで注意したいのは、Web上での文章の場合は読者のデバイス環境によって改行位置が異なる点です。 最近のWebページはレスポンシブWebデザインといって画面サイズに合わせてレイアウトが変わる仕組みになっているのが一般的です。そのため良かれと思って入れた改行が、読者の環境によっては思わぬ場所で改行が入ってしまうおそれもあります。
PCで読む場合とスマホで読む場合では適した改行バランスが異なる前提で、スマホで読まれることが多い文章であれば、スマホを基準に改行を入れたほうが安全でしょう。
漢字だらけではなく、ひらがなを入れる
あえて漢字をひらがなにすることも、読みやすさにつながります。たとえば直前の文章では「つながります」とひらがなで書きました。一般的には「繋がります」と漢字で表記しますが、ひらがなにすることで読みやすくなるためです。
このように、漢字をひらがなで表記することを「ひらく」と言います。
書籍や新聞などの印刷物や、企業の広報が発信する文章、役所などが発信する公的な文章を書く場合には、共同通信社の『記者ハンドブック』や朝日新聞社の『朝日新聞の用語の手引』、時事通信社の『最新 用字用語ブック』がガイドラインとしてよく利用されています。これは正しい日本語で伝わる文章を書くために、送り仮名の使い方や漢字とひらがなの使い分けのほか、外来語の表記や日時・料金といった数字の記載方法が書かれているものです。
正しい表記で文章を記載する上では非常に参考になりますが、Webライティングでは、より「読みやすさ」を意識した書き方をするため、記者ハンドブックよりもひらがなの比率を増やす場合が多いです。
たとえば「AがBだと判る」という一文があった場合に、記者ハンドブックを参照すると「分かる」と記載します。しかしWebライティングの場合は「わかる」とひらいたほうが読みやすくなりますよね。
かといって、やみくもにひらがなにすれば読みやすくなるわけではありません。できれば記者ハンドブックなどを参考にして漢字の使い方を理解した上で、どの漢字をひらくか判断を行うのがおすすめです。またクライアントによっては細かくレギュレーションを指定してくる場合があるので、バランスを見ながら漢字をひらく判断をするとよいでしょう。
それ以外にも難しい漢字や熟語が多い文章は、堅苦しい印象を与えがちです。 たとえば「宜しくお願い致します。」と漢字で書かれると堅苦しい印象にならないでしょうか?
それよりも「よろしくお願いいたします。」と書いたほうが親しみやすい印象を与えます。
また「敢えて」「態々」など漢字で記載してしまうと、読者が読み下せなかったときに「この文章は自分にはわかりにくい」と嫌気がさしてWebページから離脱してしまう可能性があります。普段使わないような漢字や常用外の漢字はできるだけ使わないようにしましょう。
文章を書く時には、標準の書き方を頭に入れたうえで「この漢字はひらがなのほうが読みやすいか?」「もっとやさしい言い回しはないか?」を意識して、ひらがなが多めの文章で書いたほうが読みやすくなります。
簡潔に内容を伝える
バランスが良い文章にするためには、だらだらと長く文章を書くのではなく、短く、簡潔に文章を書きましょう。そのポイントになるのが、一文に複数の意味を与えない文章にする方法です。
「一文一意」とは、ひとつの文章でひとつの内容を述べることで、具体的には主語と述語が一回だけ登場する文章です。一文一意にすることで、誰が見ても理解しやすい文章になります。
また言葉のつながりが不自然だったり、修飾語が多かったりすると自然に読点が増え、読んですぐに理解しにくい文章になりがちです。そのため、読点を多用しない文章を意識するのも簡潔な文章を書くポイントです。
「読みやすい文章」を実際に書く上でのポイント
では次からは具体的に「読みやすい文章」を書く上で意識したいポイントを6つ紹介します。 以前自分で書いた文章がある方は、次のポイントを参考に文章を直して元の文章と比べてみると違いがわかりやすいでしょう。
段落や小見出し内で言いたい内容は絞る
簡潔に内容を伝える文章が読みやすい文章であることは前項で触れました。さらに、段落内で伝えたい内容をひとつに絞るとさらに読みやすくなります。
なぜなら、ひとつの段落内にいくつもの内容が含まれると、読者が「結局何を言いたかったのか?」と混乱してしまう恐れがあるからです。 そのためひとつの段落で伝えたい内容を絞る、言い換えると伝えたい内容ごとに段落や小見出しに分けて書くことをお勧めします。事前に骨組みとしてタイトル、見出し、小見出しを書き出した上で、そこに書く内容は何かを整理してからライティングすると書きやすくなるでしょう。
コンテンツ制作の観点からも、事前に見出しを設定した上でライティングしたほうが流れが明確になり必要な内容のもれを防ぐことに役立ちます。
文章を読んだ時に、解釈が一つになるようにする
読み方によって、さまざまな意味にとれてしまう文章は、わかりにくい文章です。
たとえば 「私は仕事の休憩中にスマホで話す彼の姿を見た。」 という文章では、 「私は、仕事の休憩中にスマホで話す彼の姿を見た。」(彼が仕事の休憩中) なのか 「私は仕事の休憩中に、スマホで話す彼の姿を見た。」(私が仕事の休憩中) なのか、読む方によって解釈が分かれます。
複数の解釈ができる文章は、すなわち読者にとって理解しにくい文章です。 このような場合だと、書き手の意図が伝わらない可能性もあります。そのため適切な位置に読点を打つなどして、誰が読んでも明確かつ同じ解釈が出来るようにしますしょう。
読点は、基本的に「主語の後」「文章と文章の間」「並列する単語の間」「接続詞の後」「修飾語の区切り」に打ちます。 たとえば「私は、毎日電車通勤します。」「貴重なバラのエキスが入った、美容液を購入しました。(読点がないとバラが貴重なのか美容液が貴重なのかわかりにくい)」のように読点を打ちます。
構文はシンプルに絞る
構文とは、文章の組み立てのことです。英語では主語(S)+自動詞(V)は第一文型と覚えた方もいるでしょう。 日本語でも同じように主語+補語+述語のような構文があり、この構文に沿った文章を書くと内容が明確になり、読者が理解しやすい内容になります。
小説では、文芸表現として主語と述語を倒置したり文章の一部を書かずに表現したりするなど、わざと複雑な構文にしてリズムを崩したり印象深い表現にする場合があります。しかしWebライティングの場合は情報を伝えるのが目的なので、シンプルな構文で書いたほうが格段に読みやすくなります。
特に主語と述語を明確にして、主語が複数にならないように、また修飾語を多用してごちゃごちゃしないように意識するとシンプルで読みやすい文章になるでしょう。
1文は短く
一文の文字数が多いと読みにくく感じるため、短い文章を意識することをお勧めします。一般的に読みやすい一文あたりの文字数は60~80文字程度と言われているため、80文字以内に収めるように書く習慣にすると良いでしょう。
たとえばTwitterの文字制限が140文字なので、それよりも少ない80文字だと意識して書かないとすぐに文字数オーバーしてしまいます。そのため、うまく収めるためには必然的に簡潔な文章が求められます。前項で紹介したようにひとつの文章でひとつのことを言う一文一義の文章がベストです。
文章が長くなってしまった場合や主語が複数になってしまう場合は、文章を分割して短くしたほうが読みやすくなります。たとえば「Aさんは教師だが、Aさんの兄は農業を営んでいる。」という文章は、「Aさんは教師だ。またAさんの兄は農業を営んでいる。」と一文一意の文章にしたほうが、読者が意味を理解しやすくなるでしょう。
接続詞を使う
接続詞とは、「そして」「しかし」といった文章と文章を繋げるための言葉です。接続詞がない文章は、文章同士の関連性が見えなくなりがちです。たとえばAしかしBという文章であれば、Aの文章をBが否定しているという関係性が明確になります。「しかし」は逆接の接続詞で、前の内容と逆の意味になることを示す言葉だからです。
このように適切に接続詞を用いることで明確で論理的な構成にすることができます。ただ接続詞を多用しすぎると硬い文章になってしまう上、理解しにくい文章になってしまうので、適度に使うようにしましょう。
「〜という」「こと」はできるだけ避ける
ライティングに慣れていない方は、文章に「~という」「こと」を多用しがちです。これらはどちらかというと口語的な表現に近く、文章として洗練されていない印象を与えてしまいます。また多用すると読みづらい文章になります。
たとえば「私はIoTという新しい技術に興味を持った。」の文を取り上げましょう。このばあいは「IoT=新しい技術」だと表現したいのであれば「新しい技術”である”IoT」に置き換えることができるので、「私は新しい技術であるIoTに興味を持った。」と言い換えればすっきりとします。「他人の車に落書きするということは法的に許されない。」であれば、「他人の車に落書きする行動は法的に許されない。」と言い換えられます。
この2つの表現は使わなくても意味として通じることがほとんどです。自分が書いた文章を見直してみて、このような表現があったら省くか言い換えてみると、すっきりした文章になります。
読みやすい文章を学ぶおすすめ本&本から学ぶべき内容とは
ここまでで、いくつか読みやすい文章にするポイントを紹介しました。それを踏まえて、さらに学びたい方にお勧めしたい書籍を3冊紹介します。
「伝わる! 文章力が身につく本 (基礎からわかる“伝わる!”シリーズ)」
本書は豊富な例文を用いて「どんな文章にすると伝わりやすいか」を80個のポイントに分けて解説している本です。10年近く前に出版された書籍ですが、今でも多くの方に読まれています。
著者の小笠原信之氏は新聞記者出身のフリージャーナリストで、自身でも多数の執筆を行うかたわら、大学で外国人向けに日本語を教えたり、編集学校でライター向けに記事執筆法などを教えている「日本語のプロ」です。
この本でのポイントは「主語と述語を近づける」「同じ言葉を繰り返さない」など、文章の基本や内容を豊かにする工夫についてが解説されています。それを原文と改善例、その後の解説とポイントという構成で書かれているのでわかりやすい内容でしょう。いちから文章執筆の基本を学び直したいという方にも適しています。
原文があると、改善例を見ながら自分の文章を添削してみることができますよね。短期間で効果を上げたい、実践的に学びたい、というニーズを持った方に特にお勧めです。
すっきり! わかりやすい! 文章が書ける
これは、長年朝日新聞社で記者として活躍してきた著者が書いた本です。新聞記者は簡潔な文章で正しく情報を伝えるプロで、本書でもすっきりとわかりやすい文章を書くコツを簡潔に解説しています。
特に前項でも紹介した読点の打ち方や、文章のつなぎ方などのポイントなども詳しく解説しています。他にも「主語をはっきりさせる」「余分な言葉を削る」といった無駄をそぎ落とした文章にするコツや「意見や意思はハッキリ最初に書く」「あいまいな書き方をしない」といった明確に誤解なく内容を伝えるためのコツが紹介されています。
よりシンプルで伝わりやすい文章を書きたいと考える方にお勧めです。
新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング
本書は、音楽をはじめとするポップカルチャー系ニュースを発信する人気Webサイト「ナタリー」の初代編集長を務めた唐木元氏が教えるWebライティングの本です。
ナタリーでは毎月3,000本以上の記事を配信しており、スタッフは1日何本もの記事を書いています。そこで唐木氏はスタッフが短時間で迷わずライティングできる方法を社内勉強会で教えていました。そこで教えていた内容を書籍化しているので、初心者でも手際よくライティングできるようになるにちがいありません。
たとえば同書では、情報を伝える実用的な記事を書くポイントとして「書く前に準備すること」を挙げています。構造シートと呼ばれる下書きに主眼(主旨)とパーツを書き出した後、主眼に沿っていない内容を捨てる方法は、シンプルで理解しやすい文章を書く上で参考になります。
このように読みやすい文章を書くためには、バランスが良い見た目にしたうえで、簡潔に短い文章を意識することが重要です。
「ひらがなを入れる」「文章を完結にする」など、ポイントとして挙げた内容のひとつひとつは小さなことです。しかしトータルで見ると、それらを意識したかしないかで読みやすさに格段の差が出ます。
そして読みやすい文章を書くためにもっとも重要なのは、上記のポイントを頭に入れて実際に書いてみることです。文章は書けば書くほど上手になります。何度も書くうちに、自分にとってベストな書き方や、仕上げるポイントを把握できるようになるはずです。
かくたまブログは、サイトエンジン株式会社が運営するWebライター応援メディアです。
オウンドメディア や自社サイトの運用に悩むディレクション担当者やライターの悩みを減らすための情報をお届けしています。